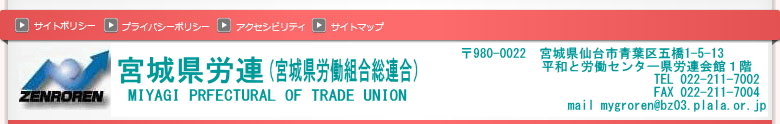1. 労働審判制度とは
労働審判制度とは,労働者個々人と経営者との間に生じた解雇・雇い止め、賃金、残業代、労働時
間、休日取得、パワハラ・セクハラなど労働に起因する紛争を対象に、最寄りの裁判所で、原則3回
以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。2006年4月
から始まった制度です。
労働審判手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働問題に関する専門的な知識経験を有する
労働審判員2名とで構成する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらない場合は
事案の実情に応じた解決をするため判断(労働審判)します。
労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
2. 制度の運用状況
制度開始からの労働審判事件の運用状況は、審理に要した期間は平均で約2か月半です。調停が成
立して事件が終了する場合が多く、労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したもの
などと合わせると、全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているものと思
われます。これは全国、宮城にも共通しています。
こうした労働審判事件の解決の状況からすると、制度導入の目的は一定程度達成されていると考え
られます。また、当事者等からも事案の実情に即した柔軟な解決が図られているとして、おおむね肯
定的な評価を受けており、事件の申立件数も年々増加しています。
なお宮城県の場合、現在は仙台地方裁判所第一、第二、第三民事部で対応しています。
3. 制度の利用に当たって
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理が終了になるため、当事者は、期日に向けて、
しっかりと主張、立証の準備をする必要があります。個々人による申立も有効ですが、短い期間で準
備し、期日において、適切な主張・立証活動を行うためには、当事者双方が、法律の専門家である弁
護士を代理人に選任することが望ましいでしょう。
また、労働者と事業主との間の紛争を解決する手続には、労働審判手続以外にも、民事訴訟、民事
調停といった裁判所が行う手続のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会などの行政機関によるあっ
せん手続、弁護士会などの法務大臣が認証した団体によるあっせん手続など、いろいろなものがあり
ます。それぞれの手続の特徴を考えて、紛争の実情により、どの手続を利用するのが良いか、検討す
ることも大切です。

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。(pdf874KB)
【タイトル】労働審判の流れのイメージ図
【注】 最高裁判所発行「ご存じですか?労働審判制度」(パンフレット)から引用